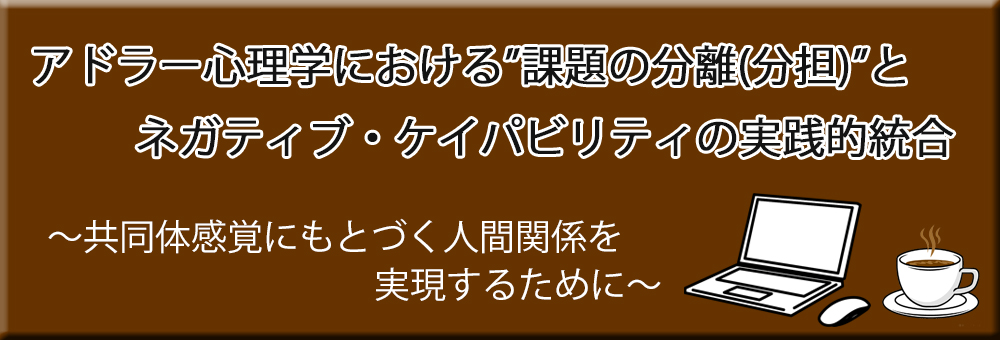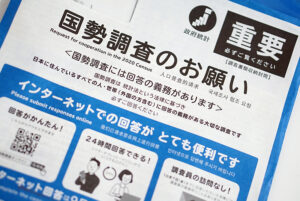RSSCあどらーカフェ勉強会 2025.11.8 ZOOM開催
今回の勉強会はZOOMで行われ、箕口先生を含め22名の参加となりました。
タイトルにある”課題の分離(分担)”とは「自分と相手の課題を明確に区別したうえで、共同の課題に取り組む」ことを意味し、「自分の課題解決に集中し、他者の課題に不要に介入しないこと」とアドラーは説いています。”ネガティブ・ケイパビリティ”とは「自らの力で困難を乗り越える能力を培う触媒の役割」という意味で、イギリスの詩人ジョン・キーツが提唱した概念です。「どうにも答えが出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」「性急に証明や理由(原因)を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力」と説明されています。
今回はこの二つを実践的に統合した場合の相乗効果について、親子関係、上司と部下、カウンセリング場面、授業中に無気力な生徒等の事例を基に学びました。”課題の分離(分担)”では「誰の課題か」を見極め、介入しすぎず、相手(相談者)を尊重し、自立と尊敬を意識することにより結果として境界が明確化されます。”ネガティブ・ケイパビリティ”では「どうにもならない不確実さ」を受け入れ、焦らず即断せず、共に「わからなさ」に耐え、忍耐と共感的受容を意識し、相手を信じることで関係の深まりと信頼が醸成されます。つまりアドラー心理学の”課題の分離(分担)”が関係の境界を明確にする理性の技法だとすれば、”ネガティブ・ケイパビリティ”はその境界の中で揺れる”人間らしさ”を支える感性の技法と位置づけられ、両者を統合することで「相手の自由と責任を尊重しながら」「不確実で結果の見えない状況を共に耐える」という成熟した人間関係が実現するということが言えます。
上記内容の箕口先生のご講義の後、2回のグループワークを行いました。「上司の曖昧な支持に振り回されて疲弊する」「母の介護をめぐる家族の葛藤」という二つのテーマで、参加者それぞれの経験に基づく意見もあり、大変有意義なワークでした。全体発表でも様々な意見があり、”ネガティブ・ケイパビリティ”を理解する参考になりました。
「”WHY”ではなく、気持ちを一緒に味わい受け止める。わからないという時間に耐え、分析・助言・解決を急がない。」…心に余裕がないタイパ重視の現代での実践は難しそうですが日々の気持ちの持ちようが大切だと思いました。箕口先生おすすめの4秒吸う、4秒止める、8秒吐くというマインドフルネス呼吸法も実践してみたいと思います。
お忙しい中、詳細な資料を作成してくださり、RSSC修了生に「仲間とのつながりや不確実で結果の見えない状況を共に耐える勇気を得られる場になれば」と講義いただける箕口先生に一同感謝しております。ありがとうございました。
12期 須藤範子