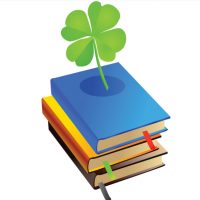2025年8月31日(日)14:00~16:00 オンライン(ZOOM) 参加者30名
この春学期は、私たちにとって特別な学期となりました。長年ご指導いただいた箕口先生の最後の講座となったからです。RSSCでの科目選択はできなくなりますが、同好会「あどらーカフェ」では、引き続き先生から学べる環境が継続します。現在、会員数は113名となり、これからの活動がますます楽しみです。さて、そんな中、今回は新たな試みとして、私、12 期生の五十嵐訓子が講師を担当させていただき、「生成 AI を利用した学習理解の試み」をテーマに勉強会を開催しました。目覚ましい進歩を遂げる AI 技術が、アドラー心理学の学習をどのように広げられるのか、その可能性を探ることを目的としました。
講座実施にあたっての工夫
講座の準備段階では、2つの重要なヒアリングを行いました。1つは、参加者の皆様を対象にした生成AIの意識調査です。利用経験や期待、課題などを事前に把握し、講座の内容に反映させました。もう1つは、箕口先生から「あどらーカフェ」の活動に対する期待や、学びのアイデアをお聞きし、それを講座にも盛り込みました。
当日は、AIに初めて触れる方から経験者まで、幅広い参加者が集まりました。私たちは、AIを学ぶための3つのステップを設け、学びを深めていきました。
① 生成AIの基本レクチャー 参加者のうち約3分の1が初心者だったため、まずは生成AIの基本的な使い方を解説しました。特に「プロンプト(質問や指示)」の工夫が回答の精度を大きく左右することを、具体例を交えてお伝えしました。これまで「正解に答える」という学習スタイルに慣れていた私たちにとって、「何を質問するか」という問いは、無限の可能性を秘めた新しい技術だと感じました。
② 生成AIを利用した体験ワーク レクチャーの後は、実践です。初心者と経験者をミックスしたグループに分かれ、「家族の献立を考える」といった身近な課題を通じて、プロンプトの作成練習を行いました。グループ内でアイデアを出し合い、具体的な条件を加えていく過程で、AI活用の面白さを実感していただけたようです。
③ アドラー心理学での学習アイデアのワーク プロンプト作成に慣れてきたところで、本題であるアドラー心理学での活用に移りました。「アドラー心理学の学びを深める」「実践の機会を増やす」という2つの課題に取り組み、それぞれの課題解決につながるプロンプトを考えました。プロンプトを作成する過程で、問題を整理し、状況を客観的に把握するといった視点を意識できるプロセスが、非常に意味深いと感じました。これは、アドラー心理学の実践的な学びに繋がる重要なステップです。さらに、時間をかけて回答を見比べたり、様々なパターンを考えたりしたかったのですが、時間が足りず、学びを深められなかったのが残念でした。
講座を終えて
最後に、箕口先生からは「AIにカウンセラーの仕事が奪われると心配する人もいるが、アウトリーチやコミュニティアプローチ、ソーシャルワークといった領域は AI にはできない。AI をうまく活用して、共同体感覚をどう醸成していくかが重要になるだろう」という総評をいただきました。
今回の勉強会は、AI 活用の可能性を感じていただけた一方で、改めて人との対話の大切さも認識する機会となりました。AI を活用しながらも、みんなでアイデアを出し合ったり、議論したり、体験を共有したりすることで、共同体感覚を高めていけると、さらに素晴らしい学びにつながると感じています。最後に、ご参加いただいた皆様に、改めて感謝申し上げます。今後も、皆さんと共に学びを深めていけることを楽しみにしています。
12期 五十嵐 訓子