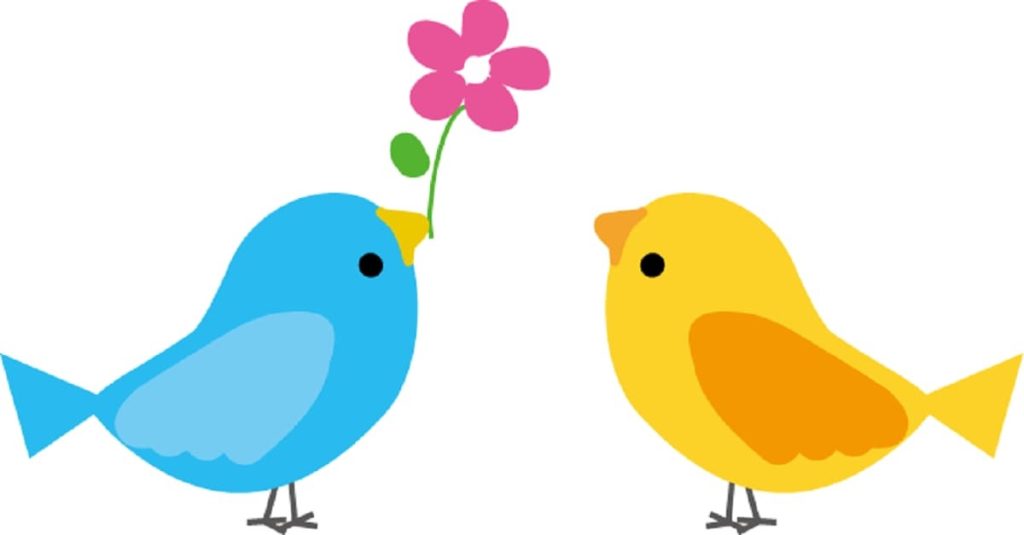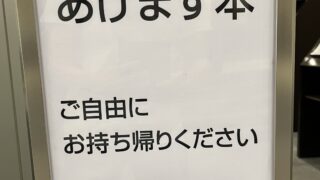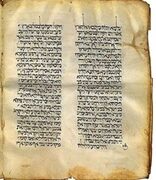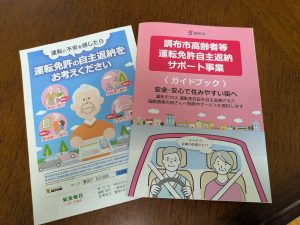残暑が残るが少しは秋の気配を感じることもあるこの時期に、太鼓と笛の音色が聞こえ今年もお囃子の練習が佳境に入って来たことを知ります。定年退職後、地域の行事に関わり始めて10年を越えた。一住民として楽しむだけだった祭りも、今では主体的な行事になった。コロナ禍でお祭りが中断された後、諸事情により祭典実行委員会を立ち上げその運営に携わってきた。
獅子舞➡
神奈川県の北部に位置する相模原市緑区下九沢塚場地区は、徳川幕府のとき庶民の間で大山講が発展して、大山街道の一つで塚場宿として賑わった。今でも旧家はその屋号が残っている。近年も東京のベッドタウンとして新築の家も増え続け、若い世帯も多く住んでいる。しかし人口は増えても世襲として続いてきた祭りの担い手探しは毎年難航する。
日本の祭りは、それぞれの地域に根ざした独自の歴史と文化を育んできた。当地区の秋祭りも応永元年(1394年)勧請されたという御嶽神社の祭礼日(8月26日)に行われる。その時に花を添えるのが獅子舞(上記写真)である。竹のささらを持つ鬼面の岡崎、剣獅子、玉獅子、巻獅子が舞うのである。その獅子舞は文政4年(1821年)に始まったとされている。例祭の余興が時を経て地域の重要な行事へと発展したのです。獅子舞は神奈川県無形文化財の指定を受け、地方紙の記者が来て新聞に掲載されることも多い。日本に20万社以上あると言われる神社で、今もなお受け継がれているであろう祭りの原風景なんですね。
しかし、祭りも時代に対応せざるを得ません。かつて7月に行われていた夏祭りは、猛暑の中での準備や参加者の負担を考慮し、一昨年から5月の子ども祭りに移行した。祭りの準備もSNSをフル活用し詳細に情報共有し、自治会は主催から協力組織という位置づけになり、祭典実行委員会が中心となって運営を担っている。
PTAや子ども会の機能が縮小し、かつてのような組織的な協力が得られにくくなってきた。そこで子ども祭りは地域の小学生の通学路を使ってチラシを配布し、また子どもたちの野球チームやドッジボールチームに協力を求めるという、新たな試みにも挑戦した。子どもたちが主体的に祭りに関わることで、より多くの参加者を呼び込みたいと考えたのです。



全国的に見ると、人口減少や担い手不足により、祭りをやめてしまう地域も少なくないようです。今後の祭りのあり方を考えると、我々は「自由度の高い祭り」を目指すべきだと感じています。これは、参加者が気負うことなく自由に参加でき、役員もそれぞれの都合に合わせて無理なく関われる仕組みを意味します。一時的なボランティアではなく、役割分担を継続的なものとすることで、担い手の育成と安定を図りたいのです。
何よりも大切なのは、子どもや若者が「祭りの楽しさ」を肌で感じて、自ら参加したくなるような祭りにすることです。体験が子どもたちの記憶に刻まれ、将来、彼らが地域を支える大人になった時に「あの祭りが楽しかったから、今度は自分たちもやろう」と思える心に残るイベントにすることです。お囃子の太鼓の音が、単なる地域の音ではなく、世代を超えて受け継がれる絆の証として、未来永劫響き渡ることを願ってやみません。
今年の祭りも数日後に迫りその準備もできた。祭りの火を絶やさぬために今年も盛り上げていこうと思う。
<<Kissの会は、RSSC同窓会ホームページへの投稿サークルです>>
【Kissの会 連絡先】 kiss7th.rssc@gmail.com
【投稿履歴/Kissの会 webサイト】https://rssc7thkiss.jimdofree.com/