フランクフルトの「グルメ教授」が勧めるドイツ料理
高橋 輝暁
(立教大学名誉教授)
新型コロナ禍はまだまだ終息していないとの警戒心が払拭されたわけではないけれど、海外からの観光客も急増している。こんな状況では、国際学術交流の観点からも、さすがにもう日本に閉じこもっているのもまずいだろう。そんな思いから、4年ぶりに50日余りのドイツ出張を敢行した。羽田空港は、海外からの搭乗客で賑わっており、食事をする場所を見つけるのにも苦労する。ヨーロッパ行きの飛行機は、ウクライナ戦争のせいで、以前のようにロシア上空を飛行できないから、北極上空のルートを飛ぶ。成田空港からアンカレッジを経由して北極上空を飛んでいた1980年代に戻ったような気分だ。コロナ禍直前に比べると2時間も余計にかかる。フランクフルトに着いたら、その空港がまた大混雑で、旅券審査場から溢れた行列が通路にはみ出していた。やっとの思いで、フランクフルト中央駅前のホテルに辿り着いたら、もうグロッキー状態。駅の売店で買ったパンをかじって寝るほかない。
翌日の昼は、旧知のドイツ文学者が「フランクフルト名物のドイツ料理」に招待してくれた。フランクフルトの北隣りの町ギーセンの大学の教授で、舌が肥えている。だから私は密かに「グルメ教授」と呼んできた。フランクフルトと言えば、ソーゼージがよく知られている。しかし、「グルメ教授」のご招待とあれば、そんなありふれた料理ではない。
珍しかったのは、「音楽とともにチーズ」という名の前菜だ。チーズのマリネとでもいうか、タマネギとキャラウエイ(セリ科の野草)、塩、胡椒などを香辛料にして、酢とオイル、それにリンゴ酒あるいは辛口の白ワインを混ぜた中に熟成チーズを漬けるらしい。極めつきが、フランクフルト流の食べ方だ。フォークを使わずにナイフだけで食べる。ナイフでチーズを切って、バターを塗ったパン切れにのせたら、タマネギとキャラウエイを加えて、口元に持っていき、ナイフで押し込む。それどころか、チーズを切ったら、それをナイフで刺して、そのまま口へ運んでも良い。
この「前菜」というか、正確には「前チーズ」と「音楽」との関係については、諸説あるそうだ。一説によると、「音楽」とはタマネギを噛むときの音だという。日本なら「シャキシャキ」と言うだろうに、フランクフルトでは、それが音楽に聞こえるのだから、面白い。たしかに「シャキシャキ」にはリズムがある。昔はレストランで音楽を弾いて回る芸人がいたので、それを聞きながらこのチーズを食べたからという説も、「グルメ教授」の蘊蓄に基づく。
今回の私の主な滞在地がベルリンということで、この「グルメ教授」がぜひ試したらと勧めてくれたのは、ドイツ料理のレストラン「税関館ルッツ」だ。ベルリンの中央部をくねくね貫通するシュプレー川の南には、そこから、引いた水が小さな運河を穏やかに流れている。この運河に沿った広い草地にたたずむ木組みの「税関館」は、ロマンチックな風情を醸し出す。その名前は、かつて行き交う船から通行税を徴収する関所だったことに由来する。そこに今はレストランが入り、屋外の草地にも、テーブル席が並ぶ。
室内で運河が見える窓側の席に陣取って、メニューを一生懸命に読んでいると、形容矛盾かと思われる言葉が目にとまった。Wollschwein(ヴォルシュヴァイン)だ。ドイツ語で「羊毛」のことをWolle(ヴォレ)というので、Woll-(ヴォル)は、語末の弱音 -eが欠落したのだろう。Schwein(シュヴァイン)は「豚」だから、直訳すれば「羊毛豚」ということになる。以前にベルリンを含むブランデンブルク地方の特産料理という触込みにつられて、Apfelschwein(アプフェルシュヴァイン)の骨付きステーキを食べた。Apfel(アプフェル)は英語のapple、つまり「林檎」なので、「林檎豚」だ。説明を聞くと、林檎を餌として育った養豚だという。たしかに、これは、容易に理解できる。しかし、いくら豚は何でも食べるといっても、「羊毛」が餌になるはずがない。
考えあぐねて、ウェイターに尋ねてみた。「羊毛」を食べて育った豚ではもちろんなく、毛がたくさん生えた豚だという。では猪の一種かと問うと、即座に否定された。やはり豚らしい。後から調べてみると、「羊毛豚」が誕生したのは、1830年代、「毛」に保護された「羊毛豚」は温度管理が不要で、飼育に手間がかからず、養豚に適していたそうだ。19世紀末までには、巻き毛も加わって、羊ほどたっぷりではないとしても、羊毛を纏ったような姿になった。猪の毛は、ごわごわしているように見えるから、確かに違う。その「羊毛豚」が、1890年頃からハンガリーで盛んに飼育され、希少種の食肉として一時、ヨーロッパで人気だった。しかし、第二次世界大戦後に脂肪が少なく肉の多い品種がイギリスからヨーロッパに広まり、「羊毛豚」は駆逐されたという。21世紀に入って、家畜についても絶滅危惧種の保全が叫ばれ、「羊毛豚」にも復活の兆しが見えている。一部の高級料理店からも注目され、新たに食通の間で人気が出ているらしい。
さっそく注文したところ、グリルした背肉のいわば棍棒が出てきたのには仰天した。太さ10センチ、長さ50センチぐらいだろうか。長すぎて、大きな皿からはみ出している。ドイツではもともとどんな料理でも1人前の量が多く、日本の感覚だと大盛りだ。それにしても、この「羊毛豚」は大きすぎる。「でか盛り」、いや、それどころではない。ところが、ひとくち食べて、ジューシーな柔らかさに魅了された。肉を包むアーモンドの味が、独特の脂の深みと相まって、「頬が落ちる」とはこういうことかと思った。しかも、肉の間に太いあばら骨が何本も挟まっている。50センチのうち、食べられるのは半分程度だから、完食も可能だった。あばら骨から剥がして食べる肉の濃厚な味わいは、自分の舌で試さないとわからない。文字通り「筆舌に尽くしがたし」。
日本にもこの「羊毛豚」を飼育している農場があるようだ。それもごく最近のことで、2016年に始まったらしい。「羊毛豚」発祥の国ハンガリーでの名称を用いて「マンガリッツァ豚」という。インターネットには、誰かがハンガリーの「食べられる国宝」と書き込んでいた。日本のレストランでも、「羊毛豚」の「あばら骨付棍棒グリル」を賞味できる日が、来るかも知れない。

© Quartl 図版出典 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mangalica-Schwein_qtl1.jpg
この記事の投稿者
最新の投稿記事
 期生会2026年1月14日14期生会 クリスマスワークショップ、懇親会開催の報告
期生会2026年1月14日14期生会 クリスマスワークショップ、懇親会開催の報告 十四期生会2025年9月27日14期生会 総会・講演会・懇親会の開催報告
十四期生会2025年9月27日14期生会 総会・講演会・懇親会の開催報告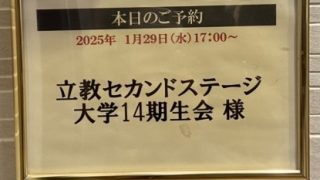 期生会2025年1月31日【14期生会】14期生会総会・懇親会 開催報告
期生会2025年1月31日【14期生会】14期生会総会・懇親会 開催報告 期生会2024年9月30日【14期生会】本科佐々木ゼミ「山と海の美術館を巡る旅」
期生会2024年9月30日【14期生会】本科佐々木ゼミ「山と海の美術館を巡る旅」



