逝った人はどこに居る?
高橋輝暁
立教大学名誉教授
立教セカンドステージ大学講師
逝った人はもうこの世にはいない、この世ではもう会えない、もう話をすることもできない――この絶対的な喪失感に基づいて、「あの世」と「この世」とを隔てる象徴を「川」に求める文化は、古来、様々な地域に認められる。わたしたちに馴染みの「三途の川」もそうだろう。仏典に由来するとはいえ、渡し船の船頭に六文銭で運賃を支払い、対岸の「あの世」に渡してもらうという俗信は、平安時代末期の日本に始まるらしい。
似たような川はギリシア神話にもある。それによると、地下の冥府には、「この世」と「あの世」とを隔てる川があり、船頭カローンが、オボロス銀貨と引き換えに、死者の魂を対岸に渡してくれる。だから、古代ギリシアでは、死者を送るときに、死者の舌の裏に銀貨を挟んだそうだ。これは、日本で死者を棺に収めるときに、六文銭をもたせるのに見合う。キリスト教では、周知のように、「あの世」は地下ではなく、天上にある。死者の魂は、祝福されて天国に迎えられるのだ。
ところが、科学的世界観が浸透して、「あの世」の話が必ずしも信憑性をもたなくなると、「人間は死んだら無に帰する」と考える人たちも多くなった。昨年、石原慎太郎(1932–2022)もそう公言して逝った。それでも、死後のことは誰にも分からないから、母を失った幼児に「ママはお空のお星さまになって見守っているんだ」と説明したりする。何かと死がクローズアップされる機会が多い近年、あの『千の風になって』(新井満訳・作曲)の歌を耳にして、静かな慰めを感じる人も少なくないはずだ。それは、この歌が「逝った人はわたしたちとともに居る」と五感で感じさせてくれるからではないだろうか。
わたしのお墓の前で/泣かないでください/そこに私はいません/眠ってなんかいません/千の風に/千の風になって/あの大きな空を/吹きわたっています//秋には光になって/畑にふりそそぐ/冬はダイヤのように/きらめく雪になる/朝は鳥になって/あなたを目覚めさせる/夜は星になって/あなたを見守る[…]
この歌の英語原詩については、作者をめぐって諸説ある。一説には、アメリカの主婦メアリー・フライ(Mary Frye, 1905–2004)が1932年に書いたという。ナチス時代が迫るドイツに残してきた母を亡くして悲嘆に暮れるユダヤ人少女を慰めるためだったという。「この世」から隔絶した「天国」に触れないこの詩のユダヤ教あるいはキリスト教らしからぬ内容を思うと、フライのこの詩はネイティブ・アメリカンに由来する詩に依拠するという異説にも、一理あるのかもしれない。
しかしながら、キリスト教世界にも、「逝った人はわたしたちとともに居る」と感じさせる詩が、ないわけではない。たとえば、19世紀ドイツの詩人フリードリヒ・リュッケルト(Friedrich Rückert, 1788–1866)の作品だ。1833年から1834年にかけて、幼い愛児の姉弟を相次いで亡くしたリュッケルトは、直ちに、その死を悼む詩を428編も書いた。仏教世界であれば、「さながら、菩提を弔って写経でもするように」といえようか。全編が詩集『亡き子を偲ぶ歌』(Kindertodtenlieder)として刊行されたのは、詩人の死後の1872年だった。
すると20世紀に入って、この膨大な詩集に、オーストリアの作曲家グスタフ・マーラー(Gustav Mahler, 1860–1911)が感銘を受け、5編の詩を選んで、それに曲をつける。完成したのは1904年のことだ。それが、声楽とオーケストラのための連作歌曲『亡き子を偲ぶ歌』として有名となり、日本のクラシック・ファンにも、広く知られている。
マーラーの連作歌曲『亡き子を偲ぶ歌』の5編だけでなく、この詩集全体を展望すると、「苦しみと歌」と題する序章では、次のような詩行がみつかる。
たしかに、愛(いと)しのわが子は 他人(ひと)の噂に 生き続ける、/そういうわが子を見るのなら、むしろ飾って見せたい、わたしの言葉で、/そのほうが 慰めになるはず、わが子に逝かれたわたしには。
逝った愛児たちは、「他人の噂」あるいは「わたしの歌」の中で「生き続ける」というのだ。父親としての詩人にとっては、「他人の噂」で「生き続ける」くらいなら、自分の詩の「言葉」の中でこそ「生き続け」てほしいだろう。それが『亡き子を偲ぶ歌』を詩作する動機となった。逝った愛児たちは、膨大な数の詩に歌い尽くされることによって、詩人の言葉の中で、詩人とだけでなく、その作品を読むわたしたちとも一緒に居るわけだ。人間を含めて「万物の存在は言葉にほかならない」という思想は、キリスト教で言えば、『ヨハネによる福音書』冒頭の名句「初めに言(ことば)があった」に通じる。
序章に続く「病いと死」の章には、逝った愛児たちを、キリスト教の「天使の歌声」に導かれる「魂」として描く詩もある。「逝った人はわたしたちとともに居る」ことを、「天使の歌声」の「響」きで聴覚的に聴かせ、天使の翼(はね)を授かった「魂」が「ふわふわ浮いて 飛」んでいる姿で視覚的に見せ、そして、その「魂」を「乗」せる「風」で触覚的に感じさせてくれる。『千の風になって』に繋がるイメージだ。
わたしの小さな魂が 別れを告げた/そのときに 優しく 響いて/聞こえてきたのは 天使の歌声、/それが 小さな魂に 教えてあげた/風に乗り ふわふわ浮いて 飛ぶ術(すべ)を。
この記事の投稿者
最新の投稿記事
 期生会2026年1月14日14期生会 クリスマスワークショップ、懇親会開催の報告
期生会2026年1月14日14期生会 クリスマスワークショップ、懇親会開催の報告 十四期生会2025年9月27日14期生会 総会・講演会・懇親会の開催報告
十四期生会2025年9月27日14期生会 総会・講演会・懇親会の開催報告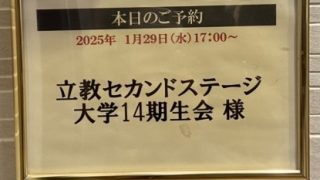 期生会2025年1月31日【14期生会】14期生会総会・懇親会 開催報告
期生会2025年1月31日【14期生会】14期生会総会・懇親会 開催報告 期生会2024年9月30日【14期生会】本科佐々木ゼミ「山と海の美術館を巡る旅」
期生会2024年9月30日【14期生会】本科佐々木ゼミ「山と海の美術館を巡る旅」



