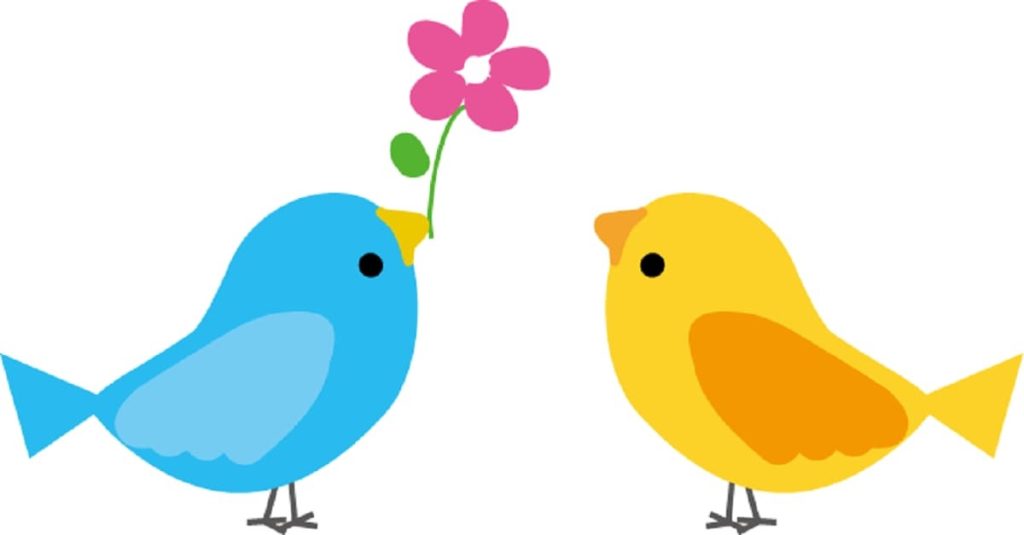外苑の緑も鮮やかに早くも夏を感じる5月、色絵を体験する機会が訪れました。色絵とは上絵具を使って器に絵付けをするものです。古九谷様式、柿右衛門様式の2点の絵皿を様式の違いに着目しながら作成する、という工芸の体験講座でした。以前から焼き物が好きで、佐賀有田の柿右衛門窯や金沢から九谷陶芸村を訪ねたり、日常に気に入った京焼や九谷焼の小皿を使ってみたりしています。
手を動かして何かを作ることに遠ざかっているこの頃、絵心ない自分を奮い立たせ体験に飛び込んでみました。初日は古九谷様式にチャレンジです。重厚な色彩と器を埋める濃密な模様が特徴と言われ、深いグリーンが魅力的に映ります。釉薬をかけ1200℃以上で焼成されたお皿の上に、先ずは転写と線描きを施します。トレーシングペーパーで転写するまでは難なく進み、ここからが本番。書黒という墨を摺り、面相筆という穂先の長い小筆で線をなぞっていく繊細な作業が続きます。墨も乾き筆も乾く・・・「大事な線は息を止めて描く」という先生の言葉に本当に息が止まったらどうする?と思うほどの緊張感。直径16センチの小さなお皿に、かじりつくように3時間、漸く黒い模様がお皿に描かれた状態になりました。次はいよいよ色のせの作業です。和絵具の黄色、緑、紫を順に厚みを出すようにたっぷり載せていきました。


2日目は、明るいトーンの優美な柿右衛門様式の絵付けに取組みます。余白の白地を生かすように、線描きは繊細に、彩色は抑制気味に、と指導されるものの細く筆を動かすのに苦心しました。「先生、鳥が恐竜のようになってしまいました。」「大丈夫、色をのせれば柿右衛門に見えるから。」と笑いながらも、鳥の目をそっと入れてくれました。
こうして2日間が終わり、2枚のお皿は工房にて800℃前後で焼成した後、我が家に送られてきました。丁寧に梱包を解き、無事に割れていなかったことに安堵しました。なんとも愛おしい気持ちが沸き起こりいつまでも手に取り眺めていました。肩も腰もガチガチになり首も回らなくなるほど大変だった作業が溶けていくような充足感に包まれている自分がいました。「工程を丁寧に積み上げていくことは、工芸の本質である。」と先生は言います。丁寧な作業は技を磨きあげ、見るものを惹きつける魅力となり「美意識」となっていくのでしょうか。


一ヶ月後、息子ファミリーと訪れた金沢は、工芸を育んだ土地の持つ力が輝くように、私たちを包んでくれました。孫娘と行った石川県立図書館には石川県の豊かな文化や風土の一端に触れられるよう、多くの蔵書とともに工芸作品が配されていました。「この金沢の地で九谷焼の世界を、自分自身の感性でみてごらん」と言う声が青い星空のような天井から聞こえてくるようでした。九谷焼への憧景はより深くなり、少しだけ、でも確かに違う景色が広がったように感じました。
色絵の体験は、工芸の奥ゆきを知る道しるべとなるのかも知れません。そして作品を生み出す土地を訪ねる喜びは、孫娘の笑顔とともに活力を与えてくれたように思います。工芸が醸し出す心地よい空間を日々愉しんでいきたいと思うこの頃です。(7期生 吉岡)
<<Kissの会は、RSSC同窓会ホームページへの投稿サークルです>>
【Kissの会 連絡先】 kiss7th.rssc@gmail.com
【投稿履歴/Kissの会 webサイト】https://rssc7thkiss.jimdofree.com/
この記事の投稿者
最新の投稿記事
 会員皆様からの投稿2026年2月21日【Kissの会 ゲスト投稿no.139】「天平の遺産を訪ねて」
会員皆様からの投稿2026年2月21日【Kissの会 ゲスト投稿no.139】「天平の遺産を訪ねて」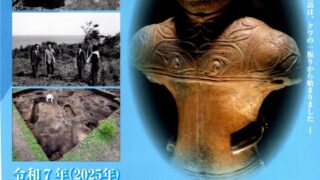 会員皆様からの投稿2026年2月11日【Kissの会 第220回投稿】「北海道・北東北の縄文遺跡群を訪ねて」
会員皆様からの投稿2026年2月11日【Kissの会 第220回投稿】「北海道・北東北の縄文遺跡群を訪ねて」 会員皆様からの投稿2026年2月1日【Kissの会ゲスト投稿no.138】「図書館が変わる時」
会員皆様からの投稿2026年2月1日【Kissの会ゲスト投稿no.138】「図書館が変わる時」 会員皆様からの投稿2026年1月21日【Kissの会 第219回投稿】「持続可能なファッションの選択」
会員皆様からの投稿2026年1月21日【Kissの会 第219回投稿】「持続可能なファッションの選択」